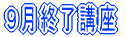
〇押し花とレジンで小物ケースor鏡をアレンジしましょう
9月2日(月)14:00~16:00参加者:14名
講師:松田ひとみさん(UVLEDレジン認定講師)
助手:日野志帆さん
最初12名で始めたのですが、途中で図書館に来られた親子が看板を
見て、6歳の娘さんがしたいと言って下さったそうで合計14名での
参加になりました。
まずは素材選び!
自分の好きな押し花やシール、ビーズなどを選ぶのですが、先生が
沢山持ってきて下さり、皆さんあれもいい!これも可愛い!と
悩みながら選ばれてました。
素材が決まったらその後は先生が説明をしながらデモストレーション
をして下さり、いよいよ自分達での作業開始!
土台の上に素材をのせていくのですが、使いたい素材が多すぎて、
思い描いていたようにはなかなかいかず、あーでもない、こーでも
ないと先生にアドバイスを頂きながら皆さん仕上げていかれてました。
最後の仕上げを先生にして頂いてる間に、使い切れなかった素材を
使って、おまけでパフェも作らせて貰いました!
鏡や小物ケースとはまた違い、美味しそうな食べ物のパーツで皆さん
素敵なパフェを作られてました!
先生も講師慣れされてましたし、助手の方もいらっしゃって、
作業もとてもスムーズに進み、時間ピッタリに終わる事が出来ました!
先生の他の作品も見て、次はブローチもいいね!とまた作りたい感じ
で皆さん満足されているようでした!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇さあ、開こう!「歌の扉」
9月11日(水)14:00~15:15
まだまだ厳しい残暑の中、たくさんの方が来てくださいました。
講師は、北後理恵さんです。
6月に取った、歌いたい歌のアンケートの中から選んだ8曲を含めて
10曲を教えて頂きました。
①喝采 (新曲) ②ふるさと
③赤とんぼ ④島唄
⑤涙そうそう ⑥蘇州夜曲
⑦少年時代 ⑧秋桜
⑨誰もいない海 ⑩思い出の渚
「喝采」は、ちあきなおみの懐かしいヒット曲です。
「ふるさと」は、二重唱できれいに歌えました。
④と⑤は、二曲続けて沖縄の歌です。
「蘇州夜曲」は、言葉の最後を繊細に、二小節ずつまとめて歌うと
より上手に聞こえる、とアドバイスを頂きました。
「誰もいない海」はトワエモアの、「思い出の渚」はワイルドワンズ
のヒット曲です。参加された人から、「ふるさと」や「秋桜」は、
歌詞が胸にジ~ンときて涙が出そうになった、感激して良かった、
とのお声を頂きました。
次回は、前半「小さな舞台で歌おうよ!2024」を開催します。
10人程度のグループごとに小さな舞台で歌うものです。
5曲のなかからエントリー曲を1つ選んで提出していただきました。
記入無しの方も当日参加で楽しんでいただければと思います。
北後先生、楽しい時間をありがとうございました。
43名の参加でした。次回は10月9日 コミスペで開催予定です。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇朝の切り抜きカフェ
9月12日(木)10:30~11:30
参加者:7名
もうすぐ9月の半ばなのに残暑厳しいからか、今回の参加者は
いつもの半分くらいだったので一人当たりのトークタイムも長めに
とれ、コーヒーを飲みながら頭の活性化ができました。
★イラストレーターが盗作疑惑を吹っ掛けられて4年間仕事を失った
( 毎日新聞より )
★舌も筋肉でできているので、高齢になると、鍛えなければ衰えて
しまうパタカラ体操→「パタカラ」を一日10回言うといいらしい
★韓国も少子高齢化で、東南アジアの労働者を多く受け入れている
★軍事一体、ふみこむ日米 ( 朝日新聞より )
以上のテーマを中心にいろんな情報交換や意見交換を楽しみました。
.jpg)
.jpg)
〇ほんのひろば (共催:山田駅前図書館山田分室)
9月14日(土)14:00~15:30
(参加者・子供16名)
(1)図書館からの本の紹介(図書館司書)
十五夜に因んで、お月様や秋の行事の本の紹介をして下さいました。
①お月様こんばんわ
②ぼくお月さまとはなしたよ
③太陽と月
④月をみよう
⑤しばわんこの和のこころ
⑥秋から冬のしきたり
⑦秋の行事を楽しむ絵本
⑧月のちから
*まるで話しかけている様なお月様の優しい表情に、思わずにっこり
する様なお話しや、お茶目な柴犬のしばわんこといたずら好きの
みけにゃんこが登場する、おもてなしの豆知識の絵本等も紹介して
下さいました。
英語の本も多数あり、子供達も真剣にお話しを聞いていました。
(英語の絵本の紹介)
⑧まんまるお月様を追いかけて
⑨パパお月様とって
⑩ぼくのともだちおつきさま
⑪グッド evening Dear Moon
⑫First Full Moon
⑬ムーンジャンバー
⑭グッド モーニング ムーン
⑮Good night moon
(2)コーラス(コールKI)
曲目
①365日の紙飛行機
②夏の思い出
③虫のこえ
④ふるさと
⑤いのちの歌
⑥ドレミの歌
⑦さんぽ(となりのトトロ)
⑧勇気100%(忍たま乱太郎)
⑨わんだふるプリキュア evolution!!
*前半は、優しい歌声とピアノの伴奏で心が和みました。
後半は、子供達に人気のアニメの曲で子供達も口ずさみながら
楽しそうに聴いていました。
鈴虫やコオロギ等可愛いイラストのうちわを使用して、見ても楽しい
コンサートでした。
(3)ともこ先生の工作
「十五夜お月様」(内山知子先生)
十五夜のお月様の工作をしました。光を当てると黄色の満月の中に
うさぎの影が映る様に工夫されており、子供達も驚いていました。
うさぎのポーズを決めるのに子供達は目を輝かせながら取り組み、
お団子のシール貼りや難しいすすきの絵も上手に描いていました。
個性が溢れ、満月も大小があり出来上がるとほっこりする作品でした。
子供達も自然と笑顔になれる時間でした。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇英語を楽しみましょう
9月21日(土)講師;アイザック マクマナスさん
・初級クラス 10:00~10:50 参加者24名
参加者 24名が4つのテーブルに分かれて、まず最初に「心斎橋」
や「嵐山京都」など16か所の中から一か所づつを他のメンバーに
Have you ever been to.....?(・・・・へ行ったことがあります
か?)と尋ね、・・・へ行ったことがある人の名前を記入して行く
デスカッションを行いました。
次に「結婚した」や「バッグを盗まれた」等15のスチュエーション
での会話を楽しみ、最後に Have you ever tried......
(・・・・を試したことがありますか?)とか
Have you ever seen...
(・・・・を見たことがありますか?)等の動詞を変えて会話を楽し
みました。
最初はテーブルのメンバー5~6人での会話だったのが、後半からは
テーブルを超えて色々な方々と会話を楽しまれており、大いに盛り
上がって和やかに開催されました。
・上級クラス 11:10~12:00参加者10名
参加者10名が2つのテーブルに別れて
(あなたならどうしますか?)
I would bring......because....
との会話で 16のスチュエーションが出され会話を楽しまれました。
まず例文の空欄にはどの語句が入るか?(tell→told)とか
(see→sow)等の設問に答えた後、各スチュエション毎にテーブル内
でのデスカッションを行った。
例; If your best friend told you they had cheated in an exam,
would you tell your teacher?
(もしあなたの親友がテストでカンニングをしたと言ったら、あなた
は先生に言いますか?)
上級の方々は流暢に各テーブルで話合われて、時間いっぱいまで会話
を楽しまれました。
〇井戸端倶楽部 (共催:西山田地区福祉委員会)
*9月12日(木)13:30~15:00
参加者:16名
リコーダーアンサンブル デブタン:14名
スタッフ:15名
(ピアノ1名・トライアングル2名・社協1名・実習生1名含)
合計45名
午後1時30分~ 体操
午後1時40分~
ピアノ伴奏で「とんび」「月の砂漠」「故郷の空」「学生時代」
を歌い、その後 ハーモニカ伴奏で「証城寺の狸囃子」
「手のひらを太陽に」を歌った。
午後2時~2時40分
リコーダーアンサンブル デブタン によるコンサート。
1「ずいずいずっころばし」
2「川の流れのように」
3 楽器紹介 ソプラノでは「月」
アルトでは「どんぐりころころ」
テナーでは「証城寺の狸囃子」
バスでは「水戸黄門」
4 ポールモーリアメドレー曲「恋は水色」「オリーブの首飾り」
5 「カノン」
6 曲当てクイズ 「津軽海峡冬景色」「知床旅情」
「わたしの城下町」「いい日旅立ち」
2曲同時に演奏 「お馬の親子」「結んで開いて」
「ゲゲゲの鬼太郎」「水戸黄門」
7 「浜辺の歌」
8 日本民謡メドレー 「ソーラン節」「会津磐梯山」
「金毘羅船々」
9 「また逢う日まで」
なんと20曲以上の演奏を聞かせていただいたが、バラエティーに
とんだ構成で非常に楽しい時間で、あっという間に終わってしまった。
構成で非常に楽しい時間で、あっという間に終わってしまった。
*9月26日(木)13:30~14:30
参加者:9名
かみしばい館:4名
スタッフ:14名
(ウクレレ1名・トライアングル2名・含)
合計27名
最初にお茶をいただいてからスタートしました。
午後1時30分~1時40分 健康体操
午後1時40分~1時50分
ウクレレ伴奏で「井戸端倶楽部テーマソング」「思い出の渚」
「鉄道唱歌」「いい日旅立ち」を歌い、その後ハーモニカ伴奏で
「夕やけ小やけ」「旅の夜風」「高校三年生」を歌いました。
午後1時50分?2時 お茶タイム
午後2時?2時30分 紙芝居「のっぺらぼう」「七どぎつね」お話に
引きこまれて、楽しませていただきました。
最後に「学生時代」を合唱して終了です。

.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇日本語教室「西山田あいうえお」
水曜日教室 9月4、11、18、25日
土曜日教室 9月7、14、21、28日
長い長い夏が終わり、秋の訪れがやっと忘れずにやってきたようです。
朝晩の気温がすごしやすいものとなりました。
今年の夏の1番の思い出は厳しい日差しということでしょうか。
11月には文化祭が開催されます。私たちの活動の紹介の場となります。
ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇3回連続講座 ~見えない・見えにくい子どもたちに~
さわる絵本を作りましょう
2回目 9/5(木) 14:00~16:00
3回目 9/19(木) 14:00~16:00
講師 さわる絵本たんぽぽ
協力 NPO法人 弱視の子どもたちに絵本を
目の見えない又は見えにくい子どもたちに手で触って楽しんで
もらうための絵本、「さわる絵本」、別名「手で読む絵本」を作る
講座です。昨年度に引き続き今年度も1冊の絵本を仕上げます。
8/29の1回目の講座に続き、今月は2回目と3回目の講座が開催され
ました。今年度は「たまごのあかちゃん」(かんざわ としこ 文、
やぎゅう げんいちろう 絵)を作成しました。
まずは、各ページのデザインを変更する必要があるかどうかを
検討しないといけません。できるだけ元の絵本のデザインを残したい
けれど、目の悪い方には分かりづらい構図があります。例えば、
ものが重なっている構図です。今回の絵本には三つの卵が重なって
描かれているページがありますが、このまま再現すると目の悪い
子どもたちは三つ重なった卵を一つの卵として勘違いしてしまうかも
しれません。分かりやすいよう卵はそれぞれ離し、三つ並べました。
今回は沢山の種類の動物も作らないといけません。
時には図鑑で細部を確認することもありました。
このようにデザインの確認をした後、講師の方が持参して下さった
材料を手に取り、自分達の家に眠る材料をあれこれ思い浮かべ、
どう作れば目の悪い子どもたちに絵本の内容、そして見たことのない
動物を伝えることができるのかを考えました。
「できるだけ本物に近い触り心地も伝えたい。」、
「だったら、鳥には羽毛を使ってみる?」
「じゃあ、蛇を作るなら蛇皮?」ということで羽毛も蛇皮も
使いました。
本物の動物の一部を使うのも一つの手段ですけれど、何もかも
そういうわけにはいきません。「鳥の爪はどうしよう?」と相談して
いた時に、講師が差し出してくれたのは、ビニールで覆われた細い
ケーブル。電線を覆っているビニールをはがし、筒状に丸まった
ビニールを縦に割り適当な大きさに切って爪のように尖らせると
確かに鳥の爪のようになりました。
「亀の卵が産まれるページの背景はどうしよう?」
「砂浜にしてみる?」
「じゃあ、本物の浜辺の砂を貼りつけてみる?」
「子ども達が触っても怪我しないかな?」
「触った後の手で口や目を触っても大丈夫かな?」と、
1ページを作るのに色々な角度から考えました。
それには、もちろん講師のこれまでの経験がとても役に立ちました。
そうやって、デザインとどんな材料をどう使うのかが決まると、
メンバーの手が生き生きと動き出し、あれよあれよという間に
どんどん形になっていきました。
そうやって出来上がった各パーツを台紙に貼り、とうとう講座での
作業が終了!参加者みんなで大喜びして、出来上がったページを
記念撮影しました。
出来上がったページは講師が持ち帰り、大きめの文字と点字を
貼り付け、ファイル状に綴じるために特殊なパンチで穴をあけて
下さいます。
11/2と11/3に開催される公民館の文化祭では、綴じる前の
各ページを展示する予定です。是非、ご覧になってください。
そして、よかったら、来年度、私達と一緒に「さわる絵本」を
作ってみませんか?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇あなたへ贈る「この本がアツい」
9月14日(土)10:30~12:00
参加者8名
スタッフ4名
講師 うさこさん(エアロビックインストラクター)
本をおすすめする講座ということで、どんな話をされるのかな?と
思っていましたが、お話の面白い、江坂の本屋さんにお勤めの
うさこさんの話に、次第に本好き達が引き込まれていきました。
講座は参加者のリクエストに先生がオススメをするという形で進行しました。
リクエストは…
1)史実を元にした近代史
2)心に残るショートストーリー
3)主人公が魅力的
4)恋愛なし純粋なミステリー
5)歴史とミステリー
6)青山美智子、重松清にハマってる人へ
7)老後に期待が持てる本
8)恋愛ファンタジー
9)入院中元気に笑える本
10)歴史やスパイ小説好きへのオススメ
11)図鑑好きが読みたくなる
12)ホラーで感動する
13)ファンタジー、SF以外
以上のリクエストに一つ一つ本を紹介してくださいました。
(関心のある方は公民館にお問い合わせくださいね!)
ちなみに
14)夢中になれて、いじめ、DV、虐待などのない明るい本で、
読後楽しくすっきり前向きにというリクエストは難しかったそうです。
他にも様々なジャンルの本を紹介していただきました。
翻訳物は翻訳者によって感じが全然違うこと、また出版社によって
明るい本が多い、感動的な物が多いと違うこと、また文字の大きさや
価格などが違うという豆情報も教えていただきました。
出版社別で探してみるのもおススメとの事です。
書店としては、平積みはオススメなわけではなく、納品数が多い
から置く棚がないからとのこと。やっぱり書店員の手書きポップが
1番信用できるよ!など教えてもらいました。
ちなみに講師のうさこさんの本名は嘉納芙佐子さんで、本の帯の
コメントに採用されたりとかしているそうです。また探してみます!
1時間半があっという間に過ぎてしまう楽しい講座でした。
私がオススメいただいた本は面白くて、すぐに読み終わってしまい
ました。子ども達に勧めていただいた本も話をすると、すぐに食いつ
いたので、購入しました。今まだ読み終わってないみたいですが、
面白い!って読んでます。自分達へのオススメでないものも面白そう
なので、手を出してみたいと思っています。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇漢字から読み解く萬葉集 第30回
9月28日(土)10:30~12:00
23名参加
第10弾も最終回。この講座も30回を迎えました。
講師:中西博史さん(漢検漢字教育サポーター)
待時而 落鍾礼能 雨零収 開朝香 山之將黄變
ときまちて/ふりししぐれの あめやみぬ/あけむあしたか やまのもみたむ
時節を待って降った時雨の雨が止んだ。夜の明ける朝方には山は黄葉しているだろうか。
市原王(巻8、1551)志貴皇子のひ孫。光仁天皇の長女、能登女王を
妻にするが最終官位が正五位下だったのは天皇即位の前に卒去した
可能性が高い。萬葉集には8首の短歌。
巻8の「秋の雑歌」に所収。萬葉集では時雨と黄葉を関連付けて詠む歌は多い。
この歌の情景‥夜半、作者は眠れぬまま床に横になっている。
ふと気付くと先ほどまで聞こえていた雨音がしなくなった。
晩秋になるのを待ちかねていたように降った時雨がいつの間にか
止んだようだ。夜が明けるときっと山肌は黄色く色づいていることだろう
‥作者の中で澱んで膠着していた時間が、再び動き始めるその一瞬を
切り取った佳作。
「あめやみぬ」諸本の原文(写本)は「雨令零収」。「令」は衍字か。
(間違って入った文字。脱字の反対語)「雨零収」はそのままだと
「あめふりおさまる」だが意味を取って「あめややみぬ」と5音で訓む。
「鍾礼」なぜ「シグ」とよむか?同じ韻に「重」「竜」が和音として
「ヂウ」「リウ」とあり、「鍾」にも「シウ」という音があったと思われ
る。これらは中国原音のngの音を写したものと考えられるゆえ、
「シウ」は「シグ」に借りることができる。
このように中国から入ってきた形(漢字)と音(発音)を日本人が発音で
きる音(文字)に変わるのは自然。
また、古人が発音できた音が現代人には発音できない、またその逆もある。
引馬野尓 仁保布榛原 入乱 衣尓保波勢 多鼻能知師尓
ひくまのに にほふはりはら/いりみだれ ころもにほはせ/たびのしるしに
引馬野に色付いたハンノキの原。
(その中に)入り乱れて衣を染めなさい。旅の証に。
長忌寸奥麿(巻1、57)旅の歌の多い歌人。
当時の旅は道も険しく獣や山賊に襲われる等、命に係わるほど危険な
もので、旅好きの持統上皇の行幸に従駕した折のものと考えられる。
この歌は難解。というのも「はりはら」は萩なのかハンノキなのか、
「イリミダレ」なのか
「イリミダリ」(群生を乱して衣に花の色を付けてしまう)なのか、
いずれも諸説持論あるが、本人の解説がない今では、受け止める側が
どちらとも解釈すれば差し支えないと思われる。
旅の証に衣に色を付けるのは、旅が危険であるが故にその土地の神が
宿る樹木や土に安全を祈願する道中儀礼だと思われる。
この歌の後に高市連黒人の歌がある。
「いずくにか舟泊てすらむ安礼の崎漕ぎ廻み行きし棚なし小舟」
(どのあたりに船を泊めているのであろうか、あの安礼の崎漕ぎ巡っ
て行った棚無し小舟は)
奥麿の歌は官人たちの姿を華麗に幻想的に写し取った歌で、黒人の
歌は大海に揺られて去った不安定で危なげな小舟が作者の旅愁の
表象であって、奥麿の陽と黒人の陰の陰陽が相まって宴席に集う旅人
たちの感慨を深めたであろう。旅愁は深ければ深いほど望郷の念
を高めて、潔斎して主の帰りを待つ家人とのつながりを密にすると
いうのが古代人の考え。
秋田之 穂上霧相 朝霞 何時邊乃方二 我戀將息
あきのたの/ほのうへにきらふ あさかすみ/いつへのかたに あがこひやまむ
秋の田の稲穂の上に朝霞が立ち込めて消えないのと同じで、
いったい何時になったら私のもやもやとした恋の思いは消え去るの
でしょうか。
磐姫皇后(いはのひめのおほきさき)(巻2、88)仁徳天皇の皇后。
葛城襲津彦(かづらきのそつひこ)の娘。後続外の身分から皇后に
なった初の例。
巻2「相聞」の冒頭に4首が連作となって掲載されている。
4首目が本歌
①君が行き日長くなりぬ山たづね迎へか行かむ待ちにか待たむ
(あの方の行幸は日数が長くなってしまった。山に分け入ってお迎え
に行こうか、それともこのままじっと待ち続けようか)
②かくばかり戀ひつつあらずは高山の磐根し枕きて死なましものを
(これほど恋こがれていないで、(いっそのことお迎えに出て)
険しい山の岩を枕に死んだ方がましだ)
③ありつつも君をば待たむ打ち靡くわが黒髪に霜の置くまでに
(このままずっとあの方をお待ちしよう。長く靡く私の黒髪が白髪に
変わるまでも
④秋の田の…
1首目で山道を迎えに行こうか待っていようかと逡巡し、
2首目では険しい山路でたとえ磐根を枕に死んでも待ち焦がれるより
はマシだ、3首目は私の黒髪が白髪になるまででもお待ちしようと
詠い、4首目では朝霧のようにもやもやした胸の思いは晴れそうに
もないと嘆いている。
この高度な起承転結の構成は仁徳朝の時代では作りえない技法で、
後世に作られた仮託(フィクション)といわれている。
また、①~③の歌には古歌に類歌があり、これに手を加えて④の歌を
添えて構成したと考えられる。
天皇がその種を絶やさぬよう多くの妃を持つことが当然であった時代
に皇后がそれを拒絶することは稀であり、「記仁徳」や「仁徳紀」では、
高貴で美麗な八田皇女を妃にすることを許さない非常に嫉妬深い女性
と記されている。
萬葉集の4首が後世の仮託だとすれば、このギャップは作者が磐姫に
限りない同情と憐憫とを感じてひたむきな恋に焦がれ身を焼く
女性像を作り上げたのだろうか?仁徳天皇の人柄を伺えばそれも
納得か・・・
第十一弾が決定しました。
次回は1月、新年の歌、冬の歌ほかの3首です。
萬葉集にはたくさんの秀歌がありますが、その漢字一つ一つの意味を
読み解きながらその歌の歴史と趣を味わっていく、非常に楽しい講座
です。これからも楽しみです。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
〇第328回 クラシックセミナー「土曜の午後の名曲喫茶」
9月28日(土)13:30~16:30
【 VIVA! オペレッタ 】
今回は、オッフェンバックの喜歌劇「天国と地獄」のDVD鑑賞なの
で、いつもより30分早い13時半から始まりました。
講師は、高橋一秀先生、お世話していただくのは由井さんです。
初めに先生から、作曲家や劇の内容の説明をうけました。
オッフェンバックは1819年にドイツで生まれランスで活躍した
作曲家です。オペレッタの原型を作り、「オペレッタの父」と言わ
れ、生涯に100曲ほどのオペレッタを作曲しました。
「天国と地獄」は、その中のヒット作で、フランスでのタイトは、
「地獄のオルフェ」で、日本では明治44年に「天国と地獄」
の題で初演されました。DVDは、2022年11月23日、日生劇場
での公演を収録されたもので、日本人が出演し、日本語で歌って
演じているので、物語の筋も分かりやすく、関西弁のセリフも
飛び出して笑えるところも多々ありました。
音楽面でも親しみやすいナンバーが並び、第二幕では、運動会の
徒競走でかかる有名な「天国と地獄」のギャロップが登場したりして
始めて観る人でもとても楽しめる喜歌劇でした。
高橋先生、由井さん、楽しい時間をありがとうございました。
次回は日程が変更になり、第二日曜日の10月13日(日)です。
参加者28名でした。